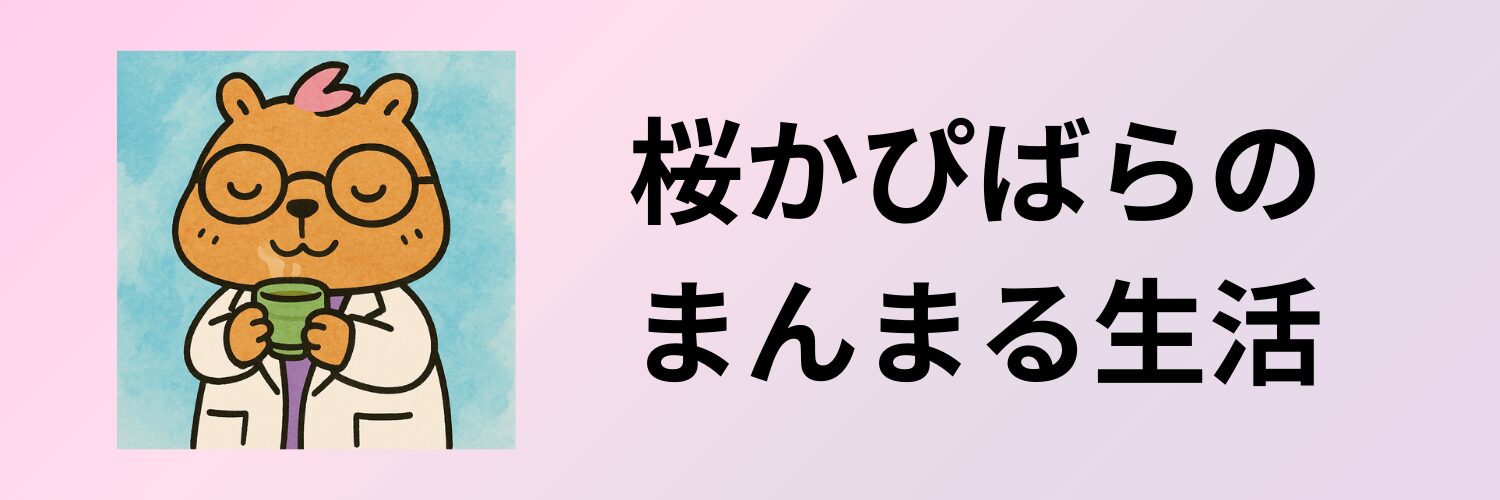*この記事のリンクには広告が含まれます。
アンデシュ・ハンセンさんの著書は最近のトレンドものが多く、今回も最近増えていると言われている発達障害の中のADHDをテーマにしたものだったので、本屋さんで見つけてすぐに購入した。
個人的な希望としては、自分自身が自閉スペクトラム症と診断されているので、「ASDの本も書いてほしい!」と強く思ったが、社会的にはADHDの診断がある人のほうが多い傾向にあり、またASDとADHDが併存している人も多い傾向なので、先に出版するとしたらADHDをテーマにするのは正解だとも思う。
私自身も自閉スペクトラム症と診断されているとはいえ、ADHDの特性を持っている感覚もあるので、そういった点ではとても興味深く読むことができた。
以下感想です。
個人的感想・気づき
・本全体の内容としては、ADHDの脳内では何が起きているのか、どんな強みがあるのか、本当にADHDの人は増えているのかなどを中心とした内容で構成されている。もし、ADHDの人はどんなことで困っていて、どんな対応をすればいいのかや、どんな仕事なら向いているかなど、生活に密着した具体的な内容を知りたいのであれば、この本は適さないと思われる。あくまでもADHDの人の脳内では何が起きているのかを理解するための本だと考えて読めば、参考になるかとは思う。
・まとめが各章の最後に書いてあるのだが、この項目だけはADHDの具体的な生活の工夫として役立つことがあるかもしれない。私自身はADHDの診断は受けていないものの、本にも書かれているとおり、誰でも少しはADHDの傾向がある部分があるので、ADHDと診断されていない人でも、参考として生活に取り入れられる工夫が見つけられると思う。たとえば、私は自閉スペクトラム症で発達支援センターに通い出し自分を分析する中で、優先順位をつけることが苦手だとわかっている。その苦手さはもしかしたらADHDの傾向のある苦手さかもしれない。この本のまとめでは、優先順位をつけることが苦手なADHDの人の話も少し出てきており、そういった人は、逆に優先順位をつけることを自分に強いるという工夫や、長期的に何を成し遂げたいかをよく考えて集中力を効率的に使うことがよい、などのアドバイスが得られた。ADHDの傾向があるかないかは人類皆グラデーションになっているというのが現在の基準なので、自分にありそうな傾向や使えそうな工夫があれば、どんどん取り入れると良いと思う。
・1冊を通して、この本を読む前から思っていたのだが、自閉スペクトラム症の診断を受けている者としては、ASDバージョンの書籍も出してほしいなと思っている。今回がADHDがテーマの本だったので、今後ASDに関しての著者の本も出版されることを期待しつつ、気長に待とうと思う。
こちらの書籍はAmazonや楽天ブックスでも購入できます。
気になった方は下記リンクからどうぞ。
Amazon:多動脳
楽天ブックス:多動脳
ここまで読んでくださりありがとうございました。